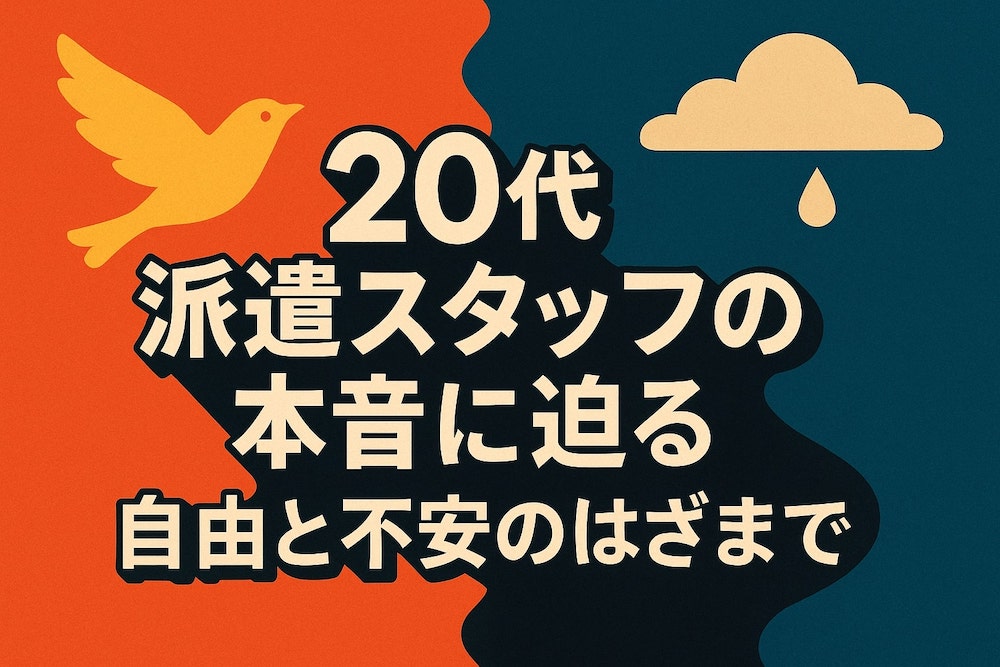執筆者:橘 美咲
目次
華やかな世界の裏側で、何が起きているのか?
雑誌の表紙を飾る美しいモデルたち、ファッションショーで颯爽と歩くランウェイの花形、SNSで何万人ものフォロワーに愛される憧れの存在。モデル業界は、多くの人にとって華やかで魅力的な世界として映っているでしょう。しかし、その輝かしい表舞台の裏側では、深刻な問題が静かに、そして確実に広がっているのです。
国民生活センターが2023年12月に発表した最新データは、私たちに衝撃的な現実を突きつけました[1]。10代・20代の女性を中心に、タレント・モデル契約関連のトラブルが急増しているのです。従来の街中でのスカウトに加え、最近ではスマートフォンで検索したオーディション情報やSNSの募集広告を通じて、自ら連絡を取ったことがきっかけとなるトラブルが目立っています。
国民生活センターの警告
「芸能事務所とタレント・モデルの契約を結んだ女性が、事務所からアダルトビデオへの出演を強く勧められる等のトラブルになっている事例も見られます」
さらに深刻なのは、芸能事務所とタレント・モデルの契約を結んだ女性が、事務所からアダルトビデオへの出演を強く勧められるといった、人権を著しく侵害する事例まで報告されていることです。これは単なる契約上のトラブルを超えた、人間の尊厳に関わる重大な問題と言えるでしょう。
私自身、かつてモデルとして活動していた経験から、この業界の光と影を肌で感じてきました。夢を追いかける若い人たちの純粋な気持ちが、時として悪意ある者たちに利用されてしまう現実を、何度も目の当たりにしてきたのです。
この記事では、モデル事務所が抱える多岐にわたる問題を、データと事実に基づいて明らかにしていきます。そして、モデルを目指す人々、現在活動中の方々、そしてその保護者の皆さんが、適切な判断を下せるよう、具体的な対策と未来への提言をお伝えします。華やかな夢を、確かな現実に変えるために、まずは真実を知ることから始めましょう。
大阪でモデル事務所をお探しならこちらのページが参考になります。
モデルが直面する具体的な問題点
不透明な契約と報酬の闇
「契約書?そんなの後で読めばいいよ。今すぐサインして!」
こんな言葉で急かされた経験はありませんか?モデル業界では、契約に関する問題が深刻化しています。レイ法律事務所の調査によると、芸能トラブルの第1位は「事務所側との契約トラブル」、第2位は「事務所側との金銭トラブル」となっており[2]、モデル業界も例外ではありません。
| 芸能トラブルランキング | 内容 |
|---|---|
| 1位 | 事務所側との契約トラブル(移籍・独立問題、権利の帰属問題など) |
| 2位 | 事務所側との金銭トラブル(報酬の未払い・不透明問題など) |
| 3位 | 事務所側によるハラスメントトラブル(パワハラ、セクハラ、枕営業の強要など) |
| 4位 | ファンとのトラブル(恋愛、ストーカー問題など) |
契約内容の不備は、まるで時限爆弾のように、後になって大きな問題を引き起こします。専属契約なのか、報酬の割合はどうなっているのか、実費負担はあるのか、契約期間はいつまでなのか。これらの基本的な事項が曖昧なまま契約を結んでしまうケースが後を絶ちません。
特に深刻なのは、報酬の未払いや遅延問題です。「今月は売上が厳しくて」「来月まで待って」といった理由で、正当な報酬が支払われないケースが頻発しています。モデルにとって、撮影やショーでの活動は貴重な収入源であり、生活の基盤でもあります。それが不当に奪われることは、単なる金銭問題を超えた人権侵害と言えるでしょう。
さらに問題となるのは、不当なマージン率の設定です。業界標準を大きく上回る手数料を徴収したり、本来モデルが負担する必要のない実費を押し付けたりする事務所も存在します。
よくある不当な費用請求
- プロフィール写真の撮影費用
- レッスン料
- 衣装代
- 交通費(本来事務所負担分)
- 宣材作成費
現代特有の問題として、肖像権や著作権、そしてSNS・YouTube権利の帰属問題も深刻化しています。レイ法律事務所の専門家も指摘するように、「最近の傾向では、事務所との契約終了時においてSNSに関する権利(YouTubeのアカウント権利も含めて)について問題になるケースが増えています」[2]。
デジタル時代において、モデルの価値は単なる撮影やショーだけでなく、SNSでの影響力にも大きく依存しています。しかし、契約書にSNSアカウントの権利帰属が明記されていない場合、事務所を辞める際に自分が育てたアカウントを失ってしまうリスクがあるのです。これは、モデルにとって将来のキャリアに致命的な打撃となりかねません。
ハラスメントという名の人権侵害
モデル業界におけるハラスメント問題は、想像以上に深刻で広範囲にわたっています。社会調査支援機構チキラボが2025年1月に公表した調査結果は、業界の暗部を白日の下にさらしました[3]。
チキラボ調査結果(2025年1月)
芸能・報道・メディア分野に従事する275名を対象とした調査では、以下の衝撃的な結果が明らかになりました:
| 被害の種類 | 経験者数 | 割合 |
|---|---|---|
| セクハラや性暴力を受けた経験 | 131名 | 51.4% |
| セクハラや性暴力の事例を聞いた経験 | 197名 | 77.3% |
| 性的接待を要求された経験 | 58名 | 22.7% |
| 性的接待を見聞きした経験 | 126名 | 49.4% |
これは、業界従事者の約2人に1人が何らかの性的被害を経験し、約4人に1人が性的接待を要求されているという、極めて深刻な状況を示しています。
調査に寄せられた自由記述には、胸が痛くなるような具体的な被害事例が記録されています。
被害者の証言(匿名化済み)
「プロデューサー・ディレクター・マネージャーからキスを要求される、腕組みを要求される、付き合おうと言われる、ホテルで裸で待っていた子がいるという話を聞かされる、何もしないからホテルに行こうと言われる、個室サウナに誘われるなど。風俗接待営業の話をされる。18年前〜今に至るまで。」
さらに衝撃的なのは、「2013年頃、テレビドラマのキャストをしていた男性俳優がプロデューサーに性的接待を強要され、断って俳優を辞めた」という事例です[3]。これは、ハラスメントが単に女性だけの問題ではなく、性別を問わず業界全体に蔓延していることを示しています。
国民生活センターの報告でも、「芸能事務所とタレント・モデルの契約を結んだ女性が、事務所からアダルトビデオへの出演を強く勧められる等のトラブルになっている事例も見られます」[1]と明記されており、ハラスメントが組織的に行われている可能性を示唆しています。
パワーハラスメントも深刻な問題です。「好きでやっているのだからそのぐらい我慢すべき」という業界特有の風潮が、被害を訴えにくい環境を作り出しています[4]。体型管理の名目で過度な食事制限を強要されたり、「太った」「ブサイク」といった人格を否定するような言葉を浴びせられたりするケースも少なくありません。
これらのハラスメントは、モデルの精神的・肉体的健康に深刻な影響を与えます。摂食障害、うつ病、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの症状に苦しむモデルも多く、中には業界を去ることを余儀なくされる人もいます。華やかに見える職業の裏で、多くの人が心身の健康を犠牲にしているのが現実なのです。
キャリア形成の壁と将来への不安
モデル業界には、「若さが全て」という残酷な現実があります。多くのモデルが20代後半から30代前半で第一線から退くことを余儀なくされ、その後のキャリア形成に大きな困難を抱えています。
しかし、問題はそれだけではありません。事務所による囲い込みや、独立を阻害する様々な仕組みが、モデルの将来の選択肢を狭めているのです。
特に問題となるのは、競業避止義務の存在です。「事務所を辞めたあと数年間は芸能活動を禁止する」という条項が契約書に盛り込まれているケースが多く、これがモデルの独立や転職を困難にしています。
競業避止義務に関する法的見解
しかし、法的な観点から見ると、このような競業避止義務には大きな問題があります。
東京地方裁判所 平成18年12月25日判決
「芸能人の芸能活動について当該契約解消後2年間もの長期にわたって禁止することは、実質的に芸能活動の途を閉ざすに等しく、憲法22条の趣旨に照らし、契約としての拘束力を有しない」
さらに、2019年には公正取引委員会も、原則として競業避止義務については事務所側に正当な理由がないとして違法(独占禁止法違反)との見解を発表しています[2]。つまり、法的には無効な条項であるにもかかわらず、多くのモデルがその存在を知らずに不当な制約を受け続けているのです。
引退後のキャリア支援の不足も深刻な問題です。多くの事務所は、モデルが現役で活動している間の収益にのみ関心を示し、引退後の人生設計については無関心です。結果として、モデル経験を活かした次のキャリアを見つけられずに困窮するケースが後を絶ちません。
これらの問題は、モデル個人の問題として片付けられがちですが、実際には業界全体の構造的な問題なのです。若い才能を使い捨てにするような現在のシステムは、持続可能とは言えません。モデル一人ひとりの人生を大切にし、長期的なキャリア形成を支援する仕組みの構築が急務と言えるでしょう。
業界構造に潜む根深い問題
歪んだパワーバランスが生む搾取構造
モデル業界の問題を理解するためには、業界全体のパワーバランスを把握することが不可欠です。チキラボの調査が明らかにしたように、実演家個人・芸能事務所・放送事業者・スポンサーという4つの主要プレイヤーの関係性の中で、最も弱い立場に置かれるのがモデル個人なのです[3]。
業界のパワー構造
スポンサー(最強)
↓ 圧力
放送事業者
↓ 圧力
芸能事務所
↓ 圧力
モデル個人(最弱)公正取引委員会が2024年12月に公表した「音楽・放送番組等の分野の実演家と芸能事務所との取引等に関する実態調査報告書」では、実演家が「芸能事務所に比して情報が少なく、交渉力も劣る」ため、不利益な契約内容のまま締結してしまう状況があると指摘されています[3]。
この構造的な問題は、まるで食物連鎖のように機能しています。スポンサーが放送事業者に圧力をかけ、放送事業者が芸能事務所に圧力をかけ、最終的にその圧力が最も弱い立場にあるモデル個人に集中するのです。
一部の悪質な事務所では、この構造を悪用した搾取が横行しています。「業界のルールだから」「みんなやっていることだから」という言葉で、不当な条件を押し付けるケースが後を絶ちません。コンプライアンス意識の低さは、業界全体の信頼性を損なう深刻な問題となっています。
興味深いことに、この権力構造は固定的ではありません。チキラボの調査では、「数字、予算、キャスティング」のいずれかの力を持つ人は優位な立場に立ちやすいため、「数字をとれる実演家」もまた大きな影響力を持つことが指摘されています[3]。
実際に、調査には「強い実演家」によるハラスメント事案も報告されています。
「強い実演家」による被害事例
「20年ほど前の話です。『●●』タレントの撮影に行ったときのことです。その人がソファに寝そべりながらマンガ本を読み、若い子はひざまづいて近くに侍っています。しばらくすると『おい、●●買って来いよ!』『早くしろよ!』といいながら、その若い子の頭を足で蹴っていました。今もテレビに出て『いい人キャラ』みたいな立ち位置のタレントですが、そのときの様子が頭にこびりついています。」[3]
このような構造的な問題は、個人の努力だけでは解決できません。業界全体のガバナンス改革と、透明性の向上が急務と言えるでしょう。
デジタル時代の光と影
インターネットとSNSの普及は、モデル業界に革命的な変化をもたらしました。従来は事務所を通じてしか仕事を得られなかったモデルが、個人で発信し、直接クライアントとつながることが可能になったのです。
デジタル化がもたらした変化
ポジティブな変化:
- 事務所の制約を受けない個人活動が可能
- 多様性に富んだ表現の創出
- フォロワー数による価値の可視化
- モデルの交渉力向上
ネガティブな変化:
- オーディション商法の巧妙化
- 誹謗中傷・なりすまし・詐欺の増加
- 個人活動モデルへの保護不足
- 新しい形の搾取構造
しかし、デジタル化は新たな問題も生み出しました。国民生活センターの報告によると、「最近ではスマートフォン等で検索して見つけたオーディションに申し込んだり、SNSに書き込まれているタレント事務所の募集広告を見たりして、自ら連絡を取ったことをきっかけにトラブルに遭うケースが散見されます」[1]とあるように、オーディション商法がより巧妙化しているのです。
SNS上では、「モデル募集」「簡単に稼げる」といった甘い言葉で若い女性を誘う悪質な業者が跋扈しています。彼らは、モデルを目指す人々の夢と憧れを巧みに利用し、高額な契約を結ばせようとします。従来の街頭スカウトと異なり、SNSでは相手の素性が見えにくく、被害に遭いやすい環境が整ってしまっているのです。
インフルエンサーモデルの台頭も、業界に新たな課題をもたらしています。従来のモデル事務所のビジネスモデルでは対応しきれない新しい働き方が生まれる一方で、個人で活動するモデルに対する保護やサポートの仕組みが不十分なのが現状です。
新しい形の被害も増加しています:
- 誹謗中傷:SNS上での心ない言葉による精神的被害
- なりすまし:モデルの名前や写真を無断使用した詐欺
- プライバシー侵害:私生活の過度な詮索や盗撮
- デジタル性暴力:画像の無断加工や拡散
これらの被害は、モデル個人の責任ではないにもかかわらず、その対応に多大な時間と労力を要求されるのです。
デジタル時代の恩恵を最大化し、リスクを最小化するためには、新しいルールと保護の仕組みが必要です。技術の進歩に法整備や業界の自主規制が追いついていない現状を、早急に改善する必要があるでしょう。
法整備の遅れと業界団体の機能不全
モデル業界が抱える多くの問題の根底には、法整備の遅れと業界団体の機能不全があります。芸能界特有の慣習と、一般的な労働法規との間には大きな乖離があり、この隙間を悪用する者が後を絶ちません。
主要な法的課題
| 課題 | 現状 | 必要な対策 |
|---|---|---|
| 労働者性の曖昧さ | 「個人事業主」扱いで労働基準法の保護を受けにくい | モデルの労働者性の明確化 |
| ハラスメント対策 | 業界特有の慣習で被害を訴えにくい | 実効性のあるハラスメント防止法 |
| 契約の透明性 | 不利益な契約内容が横行 | 契約書の標準化と情報開示義務 |
| 国際基準との乖離 | 欧米に比べて権利保護が遅れている | 国際標準に合わせた法制度整備 |
最も大きな問題の一つは、モデルの労働者性の曖昧さです。モデルは「個人事業主」として扱われることが多く、労働基準法の保護を受けにくい状況にあります。これにより、長時間労働、不当な労働条件、ハラスメントなどの問題が発生しても、適切な救済を受けることが困難になっています。
2024年秋以降、「フリーランス新法」により、フリーランスに業務を発注している事業者はハラスメント対策に係る体制整備等の措置が義務化されました[5]。これは一歩前進と言えますが、まだ十分とは言えません。モデル業界の特殊性を考慮した、より具体的で実効性のある規制が必要です。
業界団体による自主規制も、残念ながら十分に機能していません。多くの業界団体は存在しているものの、実際の問題解決や予防に向けた具体的な取り組みは限定的です。また、悪質な事務所の多くは業界団体に加盟していないため、自主規制の効果が及ばないという根本的な問題もあります。
国際的な基準と比較すると、日本のモデル業界の労働環境や権利保護は大きく遅れています。欧米では、モデルの権利を保護する法律や、業界の透明性を高める仕組みが整備されているケースが多く、日本も国際標準に合わせた改革が急務と言えるでしょう。
文化庁の「文化芸術活動に関する法的問題についてよくあるご質問」では、「事務所側にパワハラ、セクハラ、報酬の未払い等の明確な債務不履行(契約違反)がある場合は、それを理由に解除することができます」[6]と明記されていますが、実際にはこのような情報が当事者に十分に伝わっていないのが現状です。
法整備の遅れは、被害者の救済を困難にするだけでなく、健全な事業者の競争力も削いでいます。ルールが曖昧な環境では、悪質な業者が有利になり、誠実に事業を行う者が不利になるという逆転現象が起きてしまうのです。
業界の健全な発展のためには、法的な枠組みの整備と、実効性のある業界団体の設立・強化が不可欠です。そして、それらの取り組みには、業界関係者だけでなく、社会全体の理解と支援が必要なのです。
問題解決への道筋と未来への提言
モデル自身ができる自己防衛策
「転ばぬ先の杖」という言葉があるように、モデル業界の問題から身を守るためには、事前の準備と知識が何より重要です。夢を追いかける気持ちは大切ですが、同時に冷静な判断力も必要なのです。
契約書確認の重要ポイント
まず最も重要なのは、契約書の徹底的な確認です。レイ法律事務所の専門家が指摘するように、「一度契約を締結してしまうと、残念ながら、原則として契約書の内容が法律や公序良俗、社会正義に反していない限り、契約書に記載された内容がルールになってしまい、後々争うのが困難」[2]になります。
契約書で特に注意すべきポイント:
| 項目 | 確認内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 専属性 | 専属契約かどうか | 他社での活動制限の範囲 |
| 権利関係 | 芸名・肖像権の帰属 | SNSアカウントの権利も含む |
| 報酬 | 割合と計算方法 | マージン率の妥当性 |
| 費用負担 | 実費負担の有無と範囲 | 不当な費用請求の防止 |
| 契約期間 | 期間と更新条件 | 自動更新条項の有無 |
| 解除条件 | 解除事由と手続き | 双方向の解除権 |
| 制限事項 | 競業避止義務等 | 法的有効性の確認 |
これらの項目について、少しでも疑問や不安がある場合は、必ず専門家に相談することをお勧めします。「契約締結『前』に弁護士などの専門家に契約書をチェックしてもらうことが大事」[2]なのです。初期費用はかかりますが、後々のトラブルを考えれば、決して高い投資ではありません。
信頼できる事務所選びの基準
信頼できる事務所選びの基準も重要です。まず、事務所の実績と評判を徹底的に調べましょう。インターネットで検索するだけでなく、実際にその事務所に所属している(していた)モデルの話を聞くことができれば理想的です。
事務所選びのチェックポイント:
- 契約内容の透明性と説明の丁寧さ
- 報酬体系の明確さと妥当性
- ハラスメント対策の有無と実効性
- キャリア支援の充実度
- 所属モデルの満足度と定着率
- 業界内での評判と実績
相談窓口の活用
情報収集と相談窓口の活用も欠かせません。国民生活センターの消費者ホットライン(188番)[1]は、24時間365日利用可能で、専門的なアドバイスを受けることができます。また、各都道府県の消費生活センターでも相談を受け付けています。
主要な相談窓口:
- 消費者ホットライン:188番(24時間365日)
- 各都道府県消費生活センター:契約トラブル全般
- 警察:アダルト関連の出演強要など深刻な被害
- 弁護士会法律相談:法的な問題全般
アダルト関連の出演強要などの深刻な被害については、迷わず警察に相談することが重要です。
心身の健康維持
心身の健康維持も忘れてはいけません。モデル業界は外見に対する要求が厳しく、精神的なプレッシャーも大きい職業です。
健康維持のポイント:
- 定期的な健康チェック
- 適切な栄養管理(過度な食事制限は避ける)
- 十分な休息と睡眠
- 信頼できる人との関係維持
- 専門家によるメンタルケア
自己肯定感を高め、「NO」と言える勇気を持つことも大切です。
事務所と業界が取り組むべき改革
モデル個人の自己防衛だけでは限界があります。根本的な解決のためには、事務所と業界全体の意識改革と制度改革が不可欠です。
透明性の高い契約・報酬体系の確立
まず、透明性の高い契約・報酬体系の確立が急務です。契約書は平易な言葉で書かれ、モデルが理解しやすい形式である必要があります。報酬の計算方法、支払い時期、マージンの内訳などを明確に示し、後から変更する場合は必ず書面での合意を取ることが重要です。
改革すべき契約・報酬制度:
- 契約書の標準化と平易な表現
- 報酬計算の透明化
- マージン率の適正化と開示
- 支払い条件の明確化
- 変更時の書面合意の義務化
ハラスメント対策の強化
ハラスメント対策と相談窓口の設置も欠かせません。社会調査支援機構チキラボの調査が示すように、業界内でのハラスメントは深刻な問題となっています[3]。
必要なハラスメント対策:
- 定期的な防止研修の実施
- 独立した相談窓口の設置
- 相談者のプライバシー保護
- 報復防止の仕組み
- 加害者への適切な処分
事務所は、ハラスメント防止のための研修を定期的に実施し、被害を受けた場合の相談窓口を設置する必要があります。また、相談者のプライバシーを保護し、報復を防ぐ仕組みも重要です。
キャリア支援の充実
モデルのキャリア支援と教育体制の充実も重要な課題です。現役時代だけでなく、引退後のキャリア形成を支援する仕組みを整備することで、モデルの長期的な人生設計をサポートできます。
キャリア支援の具体策:
- スキルアップのための研修制度
- 他業界への転職支援
- 起業支援プログラム
- セカンドキャリア相談窓口
- 業界OB・OGとのネットワーク構築
業界倫理規定の策定
業界全体の倫理規定の策定と遵守も必要です。現在、業界団体による自主規制は十分に機能していませんが、実効性のある倫理規定を策定し、それを遵守する事務所のみが業界で活動できるような仕組みを構築することが重要です。
倫理規定に含むべき内容:
- 契約の透明性基準
- ハラスメント防止規定
- 報酬支払いの最低基準
- モデルの権利保護規定
- 違反時のペナルティ
違反した場合のペナルティも明確にし、抑止効果を高める必要があります。
社会全体で支える健全なモデル業界
モデル業界の問題解決は、業界内部の努力だけでは限界があります。社会全体で健全なモデル業界を支える仕組みが必要です。
消費者・企業の意識改革
消費者とクライアント企業の意識改革が重要な鍵を握っています。私たちが商品を購入したり、広告を見たりする際に、その背景にあるモデルの労働環境に関心を持つことが大切です。
消費者ができること:
- 倫理的な企業の商品を選択
- 問題のある企業への改善要求
- モデルの多様性を尊重
- ハラスメントを許さない姿勢
倫理的な事業を行う企業を支持し、問題のある企業には改善を求める声を上げることで、業界全体の改善を促すことができます。
メディアの役割
メディアの役割と責任も重要です。モデル業界の問題を継続的に報道し、社会の関心を高めることで、改革の機運を醸成することができます。また、モデルの多様性を尊重し、健全な価値観を発信することも重要な役割です。
法整備と国際連携
法整備の必要性についても、社会全体で議論を深める必要があります。
検討すべき法制度:
- モデルの労働者性の明確化
- ハラスメント防止法の強化
- 業界特有の問題に対応した法制度
- 国際基準に合わせた権利保護
国際的な連携も重要です。モデル業界はグローバルな産業であり、国際的な基準に合わせた改革が必要です。他国の先進的な取り組みを学び、日本の実情に合わせて導入することで、より効果的な改革が可能になるでしょう。
華やかな夢を、確かな現実に変えるために
この記事を通じて、モデル事務所が抱える問題の深刻さと複雑さをお伝えしてきました。契約の不透明性、報酬の未払い、ハラスメントの横行、キャリア形成の困難、業界構造の歪み、法整備の遅れ。これらの問題は、決して一朝一夕に解決できるものではありません。
しかし、絶望する必要はありません。問題が明らかになったということは、解決への第一歩を踏み出したということでもあるのです。国民生活センターの継続的な調査、チキラボのような研究機関による実態解明、法律専門家による問題提起、そして何より、被害を受けた方々の勇気ある告発によって、業界の闇に光が当たり始めています。
変化の兆し
変化の兆しも見えています:
- フリーランス新法の施行
- 公正取引委員会による業界調査
- 裁判所による競業避止義務の無効判決
- SNSによるモデル個人の発信力向上
法的な環境は確実に改善されつつあります。また、SNSの普及により、モデル個人の発信力が高まり、不当な扱いを受けた場合に声を上げやすくなったことも大きな変化です。
私たち一人ひとりにできること
最も重要なのは、私たち一人ひとりの意識と行動です。
モデルを目指す方へ:
夢を追いかける情熱を失うことなく、同時に冷静な判断力を身につけてください。契約書の確認、専門家への相談、信頼できる事務所選び、そして何より、自分自身を大切にすることを忘れないでください。
現在活動中のモデルの方へ:
一人で悩まず、適切な相談窓口を活用してください。あなたの経験と声が、後に続く人たちを守ることにつながります。
保護者の皆さんへ:
お子さんの夢を応援しながらも、業界の現実を理解し、適切なサポートを提供してください。時には厳しい判断が必要になることもありますが、それもお子さんの将来を守るためです。
業界関係者の皆さんへ:
短期的な利益よりも長期的な業界の健全性を重視していただきたいと思います。透明性の高い経営、モデルの人権尊重、持続可能なビジネスモデルの構築こそが、真の成功への道なのです。
社会全体での取り組み
そして、社会全体で健全なモデル業界を支えていきましょう。消費者として、メディアの受け手として、そして一人の市民として、私たちにできることがあります。問題のある企業や事務所には改善を求め、健全な取り組みを行う企業を支持することで、業界全体の改革を後押しできるのです。
モデル業界の華やかさは、決して偽りではありません。多くの人に夢と希望を与える、素晴らしい職業であることに変わりはないのです。しかし、その華やかさが一部の人々の犠牲の上に成り立っているとすれば、それは真の美しさとは言えないでしょう。
今こそ、業界全体で手を取り合い、誰もが安心して夢を追いかけられる環境を作る時です。モデルを目指すすべての人が、その才能を十分に発揮し、充実したキャリアを築けるような業界に変えていきましょう。
華やかな夢を、確かな現実に変えるために。その第一歩は、この記事を読んでくださったあなたから始まるのです。
参考文献・情報源
[1] 国民生活センター「タレント・モデル契約のトラブルにご注意!」2023年12月12日更新https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/tm_keiyaku.html [2] レイ法律事務所「芸能トラブル Q&A」
https://rei-law.com/geinou-qa [3] 社会調査支援機構チキラボ「相次ぐ芸能・メディア業界のハラスメント 実態調査から見える構造的な問題」2025年1月23日
https://www.sra-chiki-lab.com/250123column/ [4] Works Institute「性被害、パワハラ、労災・・芸能界の人権侵害に取り組む」2024年7月18日
https://www.works-i.com/works/special/no184/humanrights-14.html [5] Arts Workers Japan「私たちについて」
https://artsworkers.jp/business/ [6] 文化庁「文化芸術活動に関する法的問題についてよくあるご質問」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/kibankyoka/faq/index.html
この記事は、公開されている調査データと専門家の見解に基づいて執筆されています。個別の事案については、必ず専門家にご相談ください。